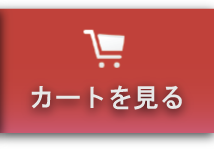インタビュー
もっと詳しく
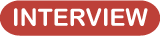
(財)日本蛇族学術研究所のヘビ博士に、
マムシの有用性についてのお話を伺いました。
「古来よりマムシは
滋養強壮に重用されてきました」
活性酸素の働きを妨げるシスタチオニン
マムシはバランスの良いアミノ酸が豊富な点が素晴らしいところです。なかでもシスタチオニンという成分は私たちの体の細胞の中に入り活性酸素の働きを妨げる働きがあります。
漢方でも滋養強壮のモト
漢方薬に使われている反鼻(はんぴ)というのはマムシの骨と内蔵を取り、筋肉を乾燥させたもの。古来よりマムシが滋養強壮のために重用されているのには、そういうことを昔の人が体験的に知っていたのだと思います。
しかし本来は、骨から内蔵まで丸ごと食べる方がミネラルもたくさん摂れて体には良いと思います。
遊離アミノ酸が溶け出すマムシ酒
マムシ酒というのも古くから伝わっていますが、マムシが腐る恐れがあるので70度くらいの高いアルコール度数のお酒に漬けます。そのとき遊離アミノ酸がアルコールに溶けだして、それが私たちの健康に良い働きをするのです。
マムシの胆とは
胆とは胆嚢(たんのう)のことですが、食べるとにがいので、やはり酒に漬けたりして飲む習慣が中国にはあります。マムシの胆汁の主成分はコール酸で、タウリンとくっついてタウロコール酸となります。これには界面活性作用があり、水に溶けない物質の消化吸収に役立ちます。他には胆汁色素としてビリベルジンという物質があり、緑色を呈します。胆が暗緑色なのはその色素の影響です。ビルベルジンは強力な抗酸化作用があるということで活性酸素から細胞を保護する機能があるようです。
最後に、現在「赤まむし」を服用されている方へ
アドバイスをいただきました
短い期間に多く飲むよりも少しずつ続けて飲まれた方が良いですね。ただし量も少なすぎると効果が上がらない場合があります。マムシは多く摂っても弊害がないので安心して摂取してください。
(財)日本蛇族学術研究所とは
文部科学省管轄の財団法人であり、日本で唯一蛇類を中心に様々な研究を行っています。一般に公開している施設のジャパン・スネークセンターでは、世界各地のいろいろなヘビを飼育展示し、年中無休でご覧になることができます。
また、「ハブの採毒実演」や「ニシキヘビとの記念撮影」、そして来園されるお客さまにもヘビを身近に感じられる様に「ヘビのふれあいタイム」など、楽しいイベントをたくさん用意してみなさんをお待ちしています。
また、医療機関や一般からのヘビに関する問い合わせも積極的にお答えしています。